ハッカの種類
01ハッカとミント

ハッカには数多くの品種があり、全世界で栽培されています。日本語では「ハッカ」ですが、英語では「Mint ミント」といい、これはラテン語の「Mentha メンタ」からきています。読み方は違えど中国語でも「薄荷」(ボーフォァ)。そして、この草の大きな特徴として、シソ科特有の正方形の茎形と、葉をもむだけで感じられるスーッとする独特な清涼感があります。これは、ハッカを代表としたハーブ類やその他植物に含まれるエッセンシャルオイルの中で、特にハッカ草に含有する精油、いわゆる「ハッカ油」によって出されるものです。ハッカ油の含有量は草の品種によっても異なリますが、一番多い「和種ハッカ」でも、重量の1~2%ほどしか含まれておらず、約10kgの収量を得るのに、最低でも一反(300坪)近くの畑が必要です。このハッカ油には、「l(または(-))-メントール」や「l-カルボン」という主成分と、その他100種類以上の成分が含まれ、これらが品種の違いによる「香りや風味」の差異を醸し出しています。そして、ハッカ属はその主成分の種類と含有量によって、大きく三種類に分けられています。
- Mentha → ギリシャ神話の女神[Menthe]の生まれ変わり
- arvensis → 原野生の
- piperascens → ペッパーに似た香りの
- spicata → 穂状をなした
和種ハッカ

Japanese mint
| 【学名】 |
Mentha Canadensis L. var. piperascens H.Hara |
|---|---|
| 【主成分】 | l(-)‐メントール |
| 【主原産地】 | インド・北米・ブラジル・ヨーロッパ・日本 |
特徴
「ハッカ脳」と呼ばれる主成分が、ハッカ草の中で最も多く「65~85%」を含有し、メントフランを含まないことでペパーミントとは区別されています。北海道には元々「ひめハッカ」を代表とする在来種がありましたが、栽培種に比べ草丈が低く油量も少なかったため、大正13年に品種決定された「あかまる」を始めとして、昭和15年前後世界の70%も生産するまでになった「ほくしん」などが品種として生まれました。昭和26年以降は「農業試験場」での品種改良が進み「ほくしん・まんよう・わせなみ」などの改良種が更に生まれ、最後の改良種「ほくと」では、「あかまる」の1haあたり3kgだった収油量が18kg前後まで上がりました。しかし、輸入自由化や合成技術の進歩によって減反が進み、現在ではごく僅かになった品種です。西洋ハッカがオイルを直接、加工品の原料として使われるのに対し、和種ハッカは主としてハッカ脳を析出する目的としながら、メントールが最も多い品種のため、副産物としてのハッカ油も精製する事が出来ました。また、和種ハッカ油は常温放置でも(特に10℃以下)結晶化しやすい性質ですが、ハッカ脳を析出することが最終目的だったために北海道の(-)温度でも保存上の不都合がなく、とても合理的な品種だったと言えます。北米やヨーロッパに分布する和種はプレゴンを多く含み、アジア東部のものはメントールを多く含むため、風味の良い品質が更に評価のされた事も、数千年のミントの歴史で日本名が品種区分の1つになった理由だと考えられています。しかし、現在は世界中に交配種も広がり、プレゴンを多く含んだ和種や原種には含まれなかったはずの「メントフラン」高含有量の和種など、各国の改良種がそれぞれに外来種との交配を続けており、境界が判然としない状況です。皮肉な事に、北見ハッカ栽培の減反のきっかけとなった輸入自由化で持ち込まれたのは、ブラジルへの移民によって育てられた北見ハッカでした。
西洋ハッカ

Peppermint
| 【学名】 |
Mentha×piperita L. |
|---|---|
| 【主成分】 | l(-)‐メントール |
| 【主原産地】 | アメリカ・インド・地中海沿岸・ヨーロッパ・ロシア |
特徴
今やハッカと言えば「ペパーミント」と言われる程、ミントの代名詞となった代表種。 スペアミントとウォーターミントの交配により出来たと言われ、和種ハッカに比べるとハッカ脳の含有量は「50~60%」と低く、特にイギリスミッチャム地方のホワイト(和名 白薄荷)と、茎が黒っぽいブラック(和名 黒薄荷)が「ミッチャム・ミント」の原種となります。単にミッチャムと言えば茎が緑色で葉が淡緑色のホワイトをさしますが、病害虫に弱く気候の影響も受けやすく、収穫時の草量・収油量も少なく高価になるため、通常はブラックが主流となり、フランス/イタリアミッチャムへと変わりながら、ヨーロッパ全土・アメリカ・中東諸国・ロシアへと広がったと言われています。 過去、「アメリカミッチャム」の一大産地は、ミシガン・インジアナ・オハイオ各州の「ミッドウエスト系」と、オレゴン・ワシントン諸州の「ファーウエスト系」に区別されていました。「西洋ハッカ」は「和種ハッカ」同様に改良が進み、近年スペアミントに多く含まれる成分を持ったものや風味が似たもの、精油の利用ばかりではなく、乾燥葉の粉砕をお茶や料理にも利用する目的の品種なども多数存在します。また、精油の特定成分のカットなどにより、香りを調整する技術も進歩し、産地別区分よりも香りの好みが優先されるべきであり、既に意味のない区分けかもしれません。
スペアミント

Spearmint
| 【学名】 |
Mentha spicata L. |
|---|---|
| 【主成分】 | l(-)‐カルボン |
| 【主原産地】 | アメリカ・インド・ヨーロッパ・ロシア |
特徴
ヨーロッパ・アメリカで料理に使う「ミント」と言えばこれをさす程、一般的な品種です。原産はヨーロッパですが、特にアメリカは85%がスペアミントの栽培で、年間2000tもの産出をします。花の穂が葉と茎の間からのスコッチ(ハイランド)と、花の穂は茎の先端に着くネイティブ(コモン)の2種類があり、スペアミントは他のミントと混在の栽培をした場合、この種のみが残って行く程繁殖力が強いミントです。西洋ハッカはスペアミント種も含んだ総称として表現される場合もありますが、基本的には、この1種のみ主成分が他の2種類と異なるために区分けされています。特にネイティブは野生種の改良種で、病害や悪天候にも強いと言われますが、スコッチの方が収量が多く、しかも香味評価も高い品種で栽培しやすい種類です。日本では19世紀初めに、オランダ船から伝えられた事から「オランダハッカ」、葉脈がくぼみ縮れている「ちりめんハッカ」、又は「緑ハッカ」とも言いますが、江戸時代当時は特異臭が嫌われ、料理にも使われず、栽培作物として定着しなかったようです。この仲間に「ホースミント」(和名 馬ハッカ)という、他の2種類とは違った風味を持つものもありますが、一般的に日本人の好む香りはメントールを主成分とする種類の方と言われ、これは主成分が「カルボン」で、その他苦味成分の「プレゴン」などが多く含まれるためだと考えられています。
02世界のハッカ
ミントは世界中で品種改良が行われ、3種類の大分類から更に分けて行くと、品種認定されただけでも100種以上、品種系統の認定期間が切れたものなどを加えると実に数百種以上とも言われます。国内薄荷の場合、「亜麻(あま)・大麻(たいま)・ちん麻・除虫菊・紫蘇(しそ)・よもぎ・菜種(なたね)・薬用けし」等の特用作物として、同時期に改良が盛んに行われました。その研究栽培は主に「寒地向き品種を北海道農業試験場」、「暖地向き品種を岡山県農試倉敷薄荷分場」が担当し、北見・岡山で作られた種類だけでも何種類になるかわからないほどの数に上ります。そして用途も、「精油を利用するもの」「葉を料理やお茶に使うもの」等、それぞれの種類によって様々です。その代表的なミントをご紹介します。
日本のハッカ
-
北見しろけ(白毛)
下湧別村在来種。耐冬性・繁殖力が弱く、ほとんど作付けされなかった品種。
1932年(昭和)7年品種決定。
-
あかまる(赤圓)
葉が丸みを帯び、茎が赤い事で付けられた名前で、大正13年に認定された戦前の代表和種。

-
ほくしん(北進)
あかまるに比べ収量が多い、倶知安地方の在来種。昭和13年に品種決定されながら、第二次大戦直前だったため普及は1950年(昭和25年)以降になった和種。

-
さんび(三美)
昭和23年、岡山県農試倉敷薄荷分場の圃場で偶然発見された「収穫率」「メントール含有量」も高い優良種。国の品種登録できないまま岡山県の奨励品種として、昭和26年以降から一気に普及した中国種。

-
まんよう(萬葉)
昭和26年に産声を上げ「北進」より対病性・収油量が良く、農家に大変喜ばれ一気に普及した和種。昭和22年、北海道農試遠軽薄荷試場で中国種「南通」と「あかまる」を交配させ、昭和28年に品種認定され、これが北交1号となる。

-
すずかぜ(涼風)北交2号
まんように比べ収油率がやや低いものの、耐倒伏性に優れ肥沃な土地向きに作られたもの。昭和28年以降から普及し始め、昭和29年に品種決定認定された和種ハッカです。

-
おおば
北海道農試遠軽薄荷試場の改良で、貿易自由化に対抗するため量産、機械化に対応する品種として登場。昭和37年認定されたが、耐病性が低く収油率も上がらなかった和種。

-
はくび(博美)
岡山農試倉敷薄荷分場で、日本在来種の青茎系との交配によって生まれた、唯一の「純日本産」と言われます。脳分は低いものの芳香性・収量が共に良く、昭和31年頃から普及し始めました。
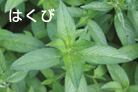
-
ほうよう(芳葉)北交8号。
ブラジルハッカや合成ハッカに対抗し「機械刈りに適した品種」として登場し、昭和37年以降から普及し始めた品種。収油率は「まんよう」の2倍以上となり、昭和40年に品種決定された「多収量・耐倒伏性」の品種。昭和34年、北海道農業試験場作物部 薄荷/防虫菊研究室において、スペアミント系野生種Mentha specata var.crispaを母とし、高脳分の和種薄荷系中間品種の「31~81」(まんよう・さんびの掛け合わせ)を父として人工交配を行い、昭和35年より実生を養成して選抜を重ねながら、昭和37年より「北交8号」の系統名で生産力や特性を検定するとともに、各地にも種根を配布して適応性を確かめたもの。

-
りょくび(緑美)
岡山県農試倉敷薄荷分場からの改良種。脳分・収量共に多く、耐干・耐熱に優れ昭和39年頃から普及し始めた品種。

-
北交10号
北海道、和種改良種。

-
あやなみ 北交12号
「機械化向き、多収量・耐病性」連作にも適し、昭和41年以降から普及した品種。「ほうよう」に代わる作付けの主力となり、昭和43年に品種決定された和種。「さんび」・「M.Spicata var. Crispa」との交配種。この頃から「高収油」に加え「芳香」の需要にも応えるべく改良がされ始めた。

-
しゅうび(秀美)
岡山県農試倉敷薄荷分場において芳香性重視に、ミッチャムミントとメントール含有量の高い「さんび」との交配で生まれた。洋種との交配のため脳分は低くなるが、ミッチャムの芳香を色濃く残し、昭和42年以降から普及し始めた品種。

-
北系5号
北海道、和種改良種。

-
北系13号
北海道、和種改良種。

-
わせなみ 北系J15号
ブラジル産ハッカの大量生産、石油合成法による合成メント-ルの出現、円の切上げ等によって、価格低迷していた和種ハッカに「10a当りの収油量が13~15kg程度」という緊急課題があたえられ、対応した多収性品種の有望系統。昭和42年「さんび」の自植第2代の極高脳分系統「J36~334」を母、スペアミント系野生種を父として人工交配を行い実生を養成、「J42~99」までの系統番号の中で選抜を重ねながら、昭和45年から生産力や特性の検定を実施、昭和48年認定された「耐病性多収性・耐倒伏性」の安定多収品種。

-
さやかぜ 北系J16号
合成ハッカの台頭によって、利用目的の絞り込みをせざるを得なくなり、まずは貼薬を目的とした品種として作られたもの。岡山の「しゅうび(秀美)」に続く、「芳香性・高脳分・多収性」の改良種。昭和43年に安定多収・連作向き品種「あやなみ」の染色体倍加系統「あやなみ四倍体」を母とし、ニホンハツカ系の高脳分・高収油率系統「北系J10号」を父として人工交配を行って実生を養成、選抜を重ねながら、昭和46年より生産力や特性の検定を行い、昭和50年に認定された和種。

-
ほくと「はっか農林11号 北斗」(北海J20号)
中国産天然ハッカと日本、米国、西ドイツの合成メント-ルの増産による価格低迷状況の下、多収で低脳分な良質なものを求める関連業界からの要望に応え、ハッカ油抽出を目的に改良された品種。昭和49年から、北海道農試作物第2部特用作物第2研究室(その後特用作物研究室)において、安定多収・中脳分品種「わせなみの人為同質倍数体」を母、ニホンハッカ系の高脳分・高収油系統「北系J20号」を父として人工交配、昭和50~51年に実生を養成と個体選抜、昭和51年以降は地下茎繁殖法で選抜を重ねながら、昭和54年から「北海J20号」として生産力や特性検定を実施、昭和55年以降から普及し、昭和57年6月「はっか農林11号」に登録され、「ほくと」と命名された「北見和種」。

-
北海JM14
和種とペパーミント種の交配種(ブラック)

-
北海JM19
和種とペパーミント種の交配種(ホワイト)

-
北海JM23号
ペパ-ミントが和種に比べ「香味性」は良好も、生草重が少なく収油率が低いため、和種はっかの品質改善を兼ねた、ペパ-ミントの多収品種の育成を図る。育成系統を「ミッチャム系和種はっか」と名付け、昭和49年に北海道農業試験場(遠軽)で多収・高収油率、良質の和種はっかの育成系統「北系J17号」を父、洋種はっかのペパ-ミントの栽培品種「ブラックミント」の倍数体を母として人工交配、昭和54年から「北海JM23号」として生産力検定試験を実施、昭和62年に品種認定された最後の北見ハッカ。草型は長太の開帳型で、茎は赤紫色。葉の緑色は濃く、アントシアンは少、形は卵形で大きく、シワは中。花は淡紫色で大きく、種子稔性は中。根茎はやや地下茎形で極太で根量は多い。

-
北海JMM3
ペパーミント種。JMM○号は、洋種系の改良を行った系統。

-
北大
北海道、和種改良種。

-
赤坂ハッカ
国内野生の和種。

-
天白ハッカ
国内野生の和種。

-
白花ハッカ
岡山種。白い花がつく種類として、分類上付けられていた。

-
岡山鏡野
岡山自生の和種。

その他の外国種
-
ウォーターミント
【学名】
M. aquatica呼び名の通り、和名も「水ハッカ」。湿地を好み、繁殖力の強い種類です。ペパーミントはこれとスペアミントの交配によって生まれた品種です。

-
ヒメハッカ
【学名】
M. japonica和名「姫ハッカ」。開拓当時に発見された北海道の在来種で、全体的に小柄ながら比較的精油量も多い種類でした。

-
ボウルズミント
【学名】
M.×villosa var. alopecuroidesミントの中で最も大きな品種。学名の「villosa」はラテン語で毛深いなどを意味しますが、学名通り丸い葉は柔らかく繊毛に覆われ、1.5m程の草丈にも成長します。

-
カーリーミント
【学名】
M. spicata var. crispa和名「ちりめんハッカ」名前の通り縮れた葉が特徴のミント。スペアミントの仲間です。

-
ホースミント
【学名】
M. longifolia和名「馬ハッカ」スペアミントの原種と言われ、古くからアジアに自生していた品種。この葉には特有の苦味があり、これをキリストの復活祭に子羊の宴の薬味として使用されていた事から、旧約聖書にあるミントは、この種ではないかと言われています。

-
コルシカミント
【学名】
M. requienii地中海西部コルシカに分布し、2~3cm程の草丈で一番小さなミント。ペパーミント系の香りを漂わせ、藤色の花を咲かせます。

-
ベルガモットミント
【学名】
M.×citrata別名「オーデコロンミント」。赤い茎と葉には赤い脈、ベルガモットに似た柑橘系の香りをさせるため、「オレンジミント」とも言われます。

-
アップルミント
【学名】
M. suaveolens和名「まる葉ハッカ」。パイナップルミントに似た葉形ですが葉に紋様はなく、リンゴの様な甘い香りが印象的なミントです。

-
ペニーロイヤルミント
【学名】
M. pulegium和名「めぐさハッカ」。別名で「ドッグミント」「プティンググラス」「アップライト」「フリーミント」などとても呼び名が多く、学名のプレギュウムとは「ノミの毒」と言う意味。ヨーロッパでは乾燥させベッド脇においておくとノミが寄らないという言い伝えがあり、家畜の敷きワラ、戸棚の防虫、生葉は肌に擦り付け、蚊よけにするなど、「葉・精油」の双方とも、防虫として使われる事が多い種類です。小さなピンクの花を咲かせペパーミント系の香りがする草丈5cm程度のかわいらしいミントです。

-
レモンミント
【学名】
M.×piperita var. citrata cv. 'Lemon'別名「ベルガモットレモン」と言われ、ベルガモットと同系種。の細身の葉形でレモンの香りがするミントです。

-
パイナップルミント
【学名】
M. suaveolens var. variegata薄緑色の葉に白のまだら模様があり、他の品種と明らかに違いのわかる種類。40cm程の草丈で一番可愛らしく、パイナップルの香りがとても印象的なミントです。

-
グレープフルーツミント
【学名】
M.×piperita ver. citrata cv. 'Grapefruit'名前と同じく、グレープフルーツの香りがするミントです。

-
ジンジャーミント
【学名】
Mentha×gracilis黄色い斑とやわらかな生姜の香りが特徴的な種類です。

-
南通
「まんよう」の改良に用いられた中国種。

-
南京
中国スペアミント種。

-
太倉
中国和種。

-
ブラックミッチャム
イギリス、ブラックミッチャム種。

-
ホワイトミッチャム
英国白ハッカ。イギリスの原種ホワイトミッチャムです。

-
ブルガロミッチャム
ブルガリアのミッチャム種。

-
フランスホワイト
ホワイトミッチャムではなく、スペアミント改良種。

-
フランスブラック
ブラックミッチャムの改良種ペパーミントです。

-
イタリアホワイト
イタリアのスペアミント改良種でペパーミント系の品種。

-
イタリアブラック
イタリアのブラックミッチャムの改良種。

-
ドイツブラック
ドイツ、ブラックミッチャムの改良種。

-
アメリカホワイト
今や一大産地のアメリカで主流のミント。スペアミント種です。

-
アメリカブラック
スペアミントが主流のアメリカですが、ペパーミントも数百トンの生産をします。ヨーロッパから渡り歩き、アメリカに根付いたブラックミッチャムの改良種。

-
ヨーロッパ和種
ヨーロッパ産の和種。アルベンシス系のハッカは世界中に存在します。

-
M.Gentilis
イタリア、スペアミント種。

-
ベルギー和種
ベルギー和種ハッカ。

-
キャットニップ
【学名】
Nepeta cataria和名「犬ハッカ」猫を陶酔させるこの香りはnepetalactoneというイリドイドを含み、ミントの香りがする種類。猫が好物のうっとりする香りと言う事がこの名の由来です。

-
コリアンミント
【学名】
Agastache rugosa別名「カワミドリ」。朝鮮半島などアジア全般に生息するミントです。

-
レモンバーム
【学名】
Melissa officinalis和名「香水ハッカ」90cmほどの背丈にもなり、葉をもむとレモンの香りがする事からこの名がつきました。
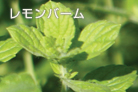
-
ヒソップ
【学名】
Hyssopus officinalis 和名「ヤナギハッカ」ハッカに似た芳香とラベンダーに似た風貌の花ハッカ。お茶などにも香水の原料としても利用されます。

-
キャットミント
【学名】
Nepeta racemosa 和名「犬ハッカ」同じ仲間のキャットニップがミントの香りがするのに対し、その成分の違いによって、こちらはミントの香りはしませんが、とても可愛らしい葉と数色の花色を持つ種類。
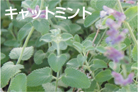
-
ホワハウンド
【学名】
Marrubium vuigare 和名「にがハッカ」ヨーロッパの北部原産、和名の通り苦味が強い、古代エジプトでは薬用として用いられた。

-
ローズゼラニウム
【学名】
Pelargonium graveolensローズ同様の主成分を含み、ミントに似た芳香のハーブ。

-
パプロカリーミント
【学名】
Mentha ?ハッカ記念館所有

-
青ぐき・赤ぐき
過去、ハッカの品種分類上の区分は、ブラックミントのように赤い茎をした品種を分類上「あかぐき」、それに対し青系の茎色のものを「あおぐき」などと区分していた頃もありました。
